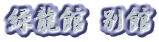| → 次のページへ | |
<2006年 12月23日> <これはナンジャ?> 年末ですねえ。クリスマスですねえ。前回のスワローが完成してから、一ヶ月以上休んでしまいましたが、今日からようやく新しいキットの製作に取り掛かりました。 <これはナンジャ?> 年末ですねえ。クリスマスですねえ。前回のスワローが完成してから、一ヶ月以上休んでしまいましたが、今日からようやく新しいキットの製作に取り掛かりました。今回のキットは、『モーガン・スリーホイーラー』。昔々、英国のモータースポーツ好きな若者を熱狂させた廉価なサイクルカー。今はソートーな金持ちでないと手に入れることは出来ません。『モギー』や『モグ』の愛称で親しまれたこの3ホイーラーのキットは、おそらく30年くらい前に発売されたファインキャストの『スーパースポーツ』後期型、バレル・バックのものが、いまだに現行で入手できますが、今回は以前にeBayのオークションで落札した“TW Collection”というメーカーの前期型ビートル・バックのモデルです。この“TW Collection”は、クラシックカーを中心に他では手に入らないかなり心惹かれる車種をいろいろ出しているようで、多分英国のメーカーだと思うのですが、どこで購入できるのかは分かりません。日本には入ってきていないようですし、『グランプリ・モデルス』を始め、海外のオンライン・ショップでも見かけたことがありません。 |
|
 ひょっとしたら、もう今は存在しない昔のメーカーかもしれないのですが、キットを見ると箱も割合新しく、ごく最近のものに見えるのです。では、なぜどこのショップでも扱っていないのか? ひょっとしたら、もう今は存在しない昔のメーカーかもしれないのですが、キットを見ると箱も割合新しく、ごく最近のものに見えるのです。では、なぜどこのショップでも扱っていないのか?まあ、実際に見てもらえれば分かりますが、現物を見たら誰も買わないような出来のキットなんですよね。エッチング・パーツが無いのはもちろん(ワイヤ・ホイールもごらんの通りキャスティングのムク)、ディテイルの再現とかは一切気に掛けず、左右のバランスなんかも気にしてない。モールドはだるくて、削ったりやすったりの跡がそのまま残っているし、一部は溶けている(!)。取説も実車の不鮮明な写真2、3枚が(コピー・グレードで)コピーされているだけ。キットだけ見たら戦前のもののような出来で、とてもこの30年のうちに作られたキットだとは思えません。ぼくもeBayで落札して届いたキットの箱を開けて、かなりショックを受けました(ーー;)。多分30年以上前のファインキャストのキットでも、こんなにイイ出来だというのに。。。 個人のモデラーが趣味で作って、知り合いに少数だけ分けているようなキットなんでしょうか?でも、なんで箱はこんなに立派なんだろう?それに、相当な種類のキットを出しているのではないかと疑われるのです(上の写真の箱にある“88”というナンバーは、どうやら製品の一連番号みたいなのです)。どなたかこのメーカーに関してご存知の方がいらっしゃったら、是非教えて欲しいですね。 実はこのキット、作る気が全く起きず見るのも嫌で、1年前の赤レンガ・ホビーフォーラムのフリマで叩き売ろうとしたのですが、いくら値段を下げてもやはり誰も持っていかない(T_T)。しかしそのとき、ひとつだけ売れ残ったこのキットを、暮れなずむ会場の雑踏の中で淋しく眺めながらフト思ったのです。これは現代の43の他のキットと比較して見るからいけないんだ・・・これはこれでこのキットとしてのみ、ひとつの存在と考えたら(?)、中々味があるではないか(゜o゜)!。43の精密カーモデル・キットではなく、ひとつのオブジェとして考えてみよう! ・・・すると製作意欲が湧いて来たんですよね。 それから一年。今まで手を付けなかったのは、やる気が萎えたのではなく、なんと一年かけて製作の下準備をしていた(?)のです。 |
|
 これは、とりあえず仮り組みしてみたところ。細部に比して全体のフォルムは、結構しっかりしています(例えば、これと比べて)。どうやらオリジナルのものらしい箱絵のスケッチを見ても、このキットの製作者は、形を捉える優れたセンスの持ち主のようです。でも細部に対するこだわりとかは全然無いんだよね。メタルの材質は、おそらく鉛が入っていない良質のピューターか、錫100%だと思います。 これは、とりあえず仮り組みしてみたところ。細部に比して全体のフォルムは、結構しっかりしています(例えば、これと比べて)。どうやらオリジナルのものらしい箱絵のスケッチを見ても、このキットの製作者は、形を捉える優れたセンスの持ち主のようです。でも細部に対するこだわりとかは全然無いんだよね。メタルの材質は、おそらく鉛が入っていない良質のピューターか、錫100%だと思います。これをどう料理するか?今回のテーマは、やっぱり「アート!」ですね。今のところ、製作の基本方針としては、下記の3点。 ① ボディの形に手を入れる。実車の形状をそのまま再現するのではなく、「アート」なので(?)ぼくのイメージで。 ② 塗装は油彩。しかし、前回のスワローとはまったく異なる技法で。実は一年前、これを作ることに決めたときから、油彩塗装にするつもりだったのですが、油絵具は30年ほど手にしていなかったため、その練習を兼ねて作ったのがウサギとスワローだったのです。 ③ 通常のディテイル・アップは施さない。当初は、ディテイル・アップを全く施さないつもりだったのですが、キットを見ていたら、スリーホイーラーのメカニカルなフロント周りをある程度は再現したくなってきました。しかしキットのプリミティブでぐちゃっ!とした存在感は、最大限生かしたいので、どのような形で手を加えるか思案中です。シャープな造形は絶対避けるつもり。 日本の43カーモデル界は、プロもアマチュアもみなさんシャープで清潔感溢れる作品作りを目指しているようで、それはそれで素晴らしいとは思うのですが、どうも画一的で全体として見たら今ひとつ面白みが無いような。。。例えば岸田さんのような個性溢れ心惹かれる作品に、最近はなかなかお目にかかれない。今回は、誰も見たことが無いような43のモデルをいっちょ作ったろか~!という大それた野望を抱いて、取り組んでみたいと思っておりますが、果たしてどうなりますことやら。途中で、やっぱりコリャ駄目だ~とほっぽり出すような事態に陥らないよう、我ながら切に祈っている次第です。 |
|
<2006年 12月27日> <Bodyの整形> 上でも紹介したVSRNサイトの四面図と比べると、確かに似たようなボディ・フォルムを捉えているのですが、実車の写真をよく見たり、“VINTAGE CARS”に掲載されている実車画像の五面図と比べてみると、やっぱりキットのシェイプは少しごろごろし過ぎみたい。ということで、まずはボディに一体成型されているシートの背板を切り取り、リアボディの中心を大胆に真っ二つに割ってしまいます。左側の矢印型の切り込みは、金鋸を間違えて入れてしまった跡ですが、気にしない。リアエンドで約2mmの巾を削り取り、切り込みラインに沿って切断面をテーパーに整形してから、左右をぎゅっと密着させて、半田を盛って溶接し、テイルの形状をふたまわりほどシェイプアップさせます。 <Bodyの整形> 上でも紹介したVSRNサイトの四面図と比べると、確かに似たようなボディ・フォルムを捉えているのですが、実車の写真をよく見たり、“VINTAGE CARS”に掲載されている実車画像の五面図と比べてみると、やっぱりキットのシェイプは少しごろごろし過ぎみたい。ということで、まずはボディに一体成型されているシートの背板を切り取り、リアボディの中心を大胆に真っ二つに割ってしまいます。左側の矢印型の切り込みは、金鋸を間違えて入れてしまった跡ですが、気にしない。リアエンドで約2mmの巾を削り取り、切り込みラインに沿って切断面をテーパーに整形してから、左右をぎゅっと密着させて、半田を盛って溶接し、テイルの形状をふたまわりほどシェイプアップさせます。もっとも、実車画像の五面図とかは、必ずレンズの歪みが出てくるので、あまりアテには出来ません。まあ、それを言っちゃえば、人間の目もレンズだから歪みがあるのですが。要するにモデルの形の整形は、「実車に合わせて正確に」ではなく、「自分が好きなように」というのが基本-これが、私の信念。 |
|
 こちらが、整形前と整形後のボディ画像上面図です。リアを割って、中心を絞っただけではなく、中心からフロントへ掛けてのラインも、半田を盛ったり削ったりを繰り返しながら全面的に手を加えました。同じキットだとは、思えない?盛り上げに使う素材は、当然半田ではなく、切り取ったシートや削り取ったボディの切り屑など、もともとのキットの素材メタルを使用します。 実は元々、キットのボディ・ラインに手を加えるのは、あまり好きではないのです。面倒臭いし、やはり原型製作者のセンスを尊重したい(?)。基本的には、原型のセンスが気に入らないキットには、手をつけるべきではないと思うのですよね。しかし、今回はシンプルなボディなので、手を加えるのがそれほど難しくないのと、リアを絞ると全体のバランスが変わって来るので、どちらにしろ全部一皮剥かなくてはいけない、ということでこうなってしまいました。 ちなみにリア後端のRは、実車ではもう少し大きいみたいですが(どちらかと云うと、元のキットのほうが近いかもしれない)、こっちのほうがカッコいいでしょ。 |
|
 こちらが整形前後のサイドビュー。フロントの冷却用アウトレットの穴は、いったん全て塞いで、あとでまた開け直すことにします。下面のラインも2mmほど削り取り、ほぼ直線にしました。全体的にかなりスリムな印象になったと思います。フロント下面の切り込みなど、まだかなり手を加えるところが残っていますが、とりあえず全体の形状は出来上がりました。 こちらが整形前後のサイドビュー。フロントの冷却用アウトレットの穴は、いったん全て塞いで、あとでまた開け直すことにします。下面のラインも2mmほど削り取り、ほぼ直線にしました。全体的にかなりスリムな印象になったと思います。フロント下面の切り込みなど、まだかなり手を加えるところが残っていますが、とりあえず全体の形状は出来上がりました。ここまで、丸三日間切った貼ったを繰り返したのですが、実のところ、とりあえず仕上がったフォルムを手にとって眺めると、最初ぼくの頭にあった漠然としたイメージとかなり違ってきてしまったため、非常に戸惑っているのです。元のキットの粘土細工みたいな(指紋の跡が残っているような)イメージを生かしたかったのですが、手を入れたところ(カッコよくはなったと思うのですが)、きれいになり過ぎちゃったような感じがします。もっと泥臭いモデルにしたかったんだけど、避けよう避けようと思っていたシャープで清潔なモデルに近づいて来ているような(?)。う~む。スタート後三日にして既に挫折か?ここからどのように形作っていくか、しばらく悩まなければなりませんな。今年の正月は休みも長いし、ずっと悩んでいよう。楽しいですね。 |
|
 <2007年 1月3日> <2007年 1月3日>年末の箱根温泉家族旅行から戻り、一日は親戚への挨拶回り。二日には早速モケイ初め。 ボディのぐるりにトリムを挟み込むための筋彫りを入れ、フロントの塞いでしまった冷却用のアウトレット・ホールを開け直します。トリムは扁平な形状を再現するため、帯金を叩いてカーブをつけようと最初は考えていたのですが、それよりも丸棒を曲げて形状を作り、ペーパーで扁平に慣らす方が手間は掛かるが簡単との結論に達し、その方法でやることにしました。0.5㎜径の燐青銅線を焼きなまして柔らかくしてから、ボディに合わせてカーブを付け、上下面を100番の粗い紙やすりで厚みが0.2、3㎜くらいになるまで薄く帯状に削ります。 |
|
 この自作帯板を凹ラインに挟み込み、しっかり押え付けながら半田で溶接。このとき、ボディを溶かしてしまわないように注意。画像で、テイルや右サイドにこびりついている塊の半田(キットのメタル素材)は、
やはり間違えて溶かしてしまったボディの補修跡です。 この自作帯板を凹ラインに挟み込み、しっかり押え付けながら半田で溶接。このとき、ボディを溶かしてしまわないように注意。画像で、テイルや右サイドにこびりついている塊の半田(キットのメタル素材)は、
やはり間違えて溶かしてしまったボディの補修跡です。帯金トリムの溶接は、下の写真を見てもらえば分かりますが、ラインに沿ってくまなく溶接したわけではなく、所々点付けで行なっています。なるべく(ボディが溶ける)リスクを減らすのと、あとで半田を削って形を整える手間を少なくするためです。ただし後でとれることがないよう、しっかり頑丈に。 ボディに半田を盛る際には、必ずキットのメタルを使い、ボディと完全に融合させなければいけません。これは、盛った半田の周囲のボディの色が変わるので(ちょっとくすむ)すぐ分かります。そのまま半田鏝を当てていると、ボディが溶け出すので気をつけること。 |
|
 これが、ボディの整形がとりあえず終了した状態。足回りは全て作り直すつもりなので、フロント下部の切り欠きも実車に合わせて形を整えておきます。通常のディテイルアップは施さないと宣言しましたが、ここまではどうも通常通り。リアのブレーキ放熱用(?)のルーヴァーは、わざと(わざとなのだ!)歪んだ筋彫りを適当に彫り入れておきます。 これが、ボディの整形がとりあえず終了した状態。足回りは全て作り直すつもりなので、フロント下部の切り欠きも実車に合わせて形を整えておきます。通常のディテイルアップは施さないと宣言しましたが、ここまではどうも通常通り。リアのブレーキ放熱用(?)のルーヴァーは、わざと(わざとなのだ!)歪んだ筋彫りを適当に彫り入れておきます。トリムと溝の隙間が残っている部分は、瞬間接着剤で固めてしまいます。 次は、足回りの工作に入ります。今一番悩んでいるのは、ワイヤホイール。キット・パーツのようなメタル・キャスティングのムクのものを使うか、エッチング製のものに取り替えるか。どちらが完成後の雰囲気に合うんでしょうね。 |
|
| → 次のページへ |
|
 Entrance Entrance トップページへもどる トップページへもどる |