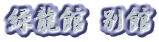|
Aston Martin DBR1/300 Le Mans 1959 Winner |
|
| → 次のページへ | |
 |
|
| 1931年の“LM5/LM6/LM7”以降、一度も欠かすことなくワークスとしてルマンに挑み続けてきたアストン・マーチンが、29年ぶりに悲願の初優勝を遂げたのがこの“DBR1”、1959年のことでした。初陣である1928年の“LM1”から数えると実に32年ぶりとなります(1929/30年はエントリーしていない)。“DBR1”は1956年のルマンでデビューしますが、途中リタイヤに終わり(この年、“DB3S”が総合2位で入賞します)、その後3年の熟成期間を経て、この年ロイ・サルヴァドーリ/キャロル・シェルビー(その後、『シェルビー・コブラ』を作り上げたその人)組が優勝、モーリス・トランティニャン/ポール・フレール組が2位に入り、文句なしの1-2フィニッシュを飾りました。 ちなみに、その後アストン・ワークスがルマン優勝を機にF1に転戦したこともあり(これは惨めな失敗に終わりますが)、2位のポール・フレールは翌年フェラーリのもとでルマンに再度挑戦、“TR59/60”でオリヴィエ・ジャンドビアンとともに見事優勝し引退の花道を飾ることになります。 |
|
 |
|
|
1959年のルマンは、従来のスポーツカー・カテゴリー(実質はプロトタイプ)に加え、市販車の参戦を促すために12ヶ月間に100台以上生産された車を対象とするGTクラスが新設され、このGTクラスは出場者53台中22台を占めました。出場車中、1955/56/57年の3年連続優勝を遂げた『ジャガー・Dタイプ』は既に往年の競争力を失い、前年優勝したフェラーリが新型の“TR59”とGTクラスの“250GT”を引っ提げて大挙参戦、エンジン・パワーのフェラーリとドライヴィング特性の優れたアストン・マーチンとの一騎打ちが当初から予想されていました。 戦いは、アストン・ワークスの作戦通り、「うさぎ」役のスターリング・モスの駆る“DBR1”が最初から跳ばしてフェラーリを引き付け、ジャン・ベーラ/ダン・ガーニィの“TR59”を共倒れに持っていきます。その後、サルヴァドーリ/キャロル・シェルビー組の“DBR1”が首位に浮上して、ジャンドビアン/フィル・ヒル組の『テスタロッサ TR59』と烈しい攻防を繰り広げました。しかし、サルヴァドーリらの“DBR1”は、車体振動悪化の為に真夜中過ぎにピットイン。原因究明に時間を費やし、ジャンドビアン/フィル・ヒル組の『テスタロッサ TR59』に追い越され大きく水を空けられてしまいます。二日目の朝、“TR59”はアストンに3周の大差を付けたうえその差をじりじりと広げ、ほぼ勝負は決まったかに見えましたが、なんと20時間目に今までの無理が祟ったのか、白い水蒸気を吹き上げながらオーバーヒートで突然のピットイン、辛うじて復帰しますが2ラップだけでよろよろとまたピットに戻り、その後二度と走り出すことはありませんでした。こうして余すところ最後の4時間で首位に返り咲いたアストン・マーチンが念願の初優勝を、それも1-2フィニッシュで遂げたのです。3位から6位までは、ポルシェ勢やジャガー・Dタイプの脱落のため、『フェラーリ250GT』が占めることになりました。 |
|
 |
|
|---|---|
|
戦後間もなく、またもやの財政危機からアストン・マーチンは「ザ・タイムズ」紙に身売り希望の広告を出しますが、これを買い取ったのが当時英国有数の実業家であったデイヴィド・ブラウン。“DB”は彼の頭文字です。その後間もなくブラウンは『ラゴンダ』も買収し、1948年に『アストン・マーチン・ラゴンダ
リミテッド』が発足、ラゴンダにいたW.O.ベントレー設計のDOHC6気筒エンジンが、1950年代の末に至るまで、アストンとラゴンダに搭載されたほぼ全てのパワーユニットのベースとなります。 レース活動の重要性を深く認識し根っからのエンスージアストであったブラウンは、当初からレーシング・スポーツカーの開発と、それを利用した市販車の販売に力を注ぎます。ワークス・スポーツカーとして開発された“DB2”や“DB3”、大成功を収めた“DB3S”のレース参戦とともに、その市販車モデルや四座タイプの“DB2/4Mk.I~III”が一般のユーザーに提供されました。 |
|
 |
|
|
“DBR1”は、“DB3S”の後継車として開発されたもので、サスペンションは、フロント‐ダブルトレーリング・アーム、リアは平行トレーリング・アームとドディオン・アクスル、前後ともにトーション・バーという、レーシング・アストンの伝統を基本的に踏襲したものですが、シャシーは従来の大径鋼管ラダー・フレームから、小径鋼管スペースフレームに変更され、5段ギアとなりました。余談ですが、この『デイヴィッド・ブラウン社』製のギアボックスは、「凶悪」な操作性で、DBR1の一番の弱点だったといいます。当時ドライヴァーは全員、テストもしてみたマセラティ製のギアボックスを好みましたが、もちろん変更は赦されませんでした。 “DB3”や“DB3S”が戦前のアウトウニオン・GPカーを生み出し、デイヴィッド・ブラウンが迎え入れたエベラン・フォン・エベルホルストの手によるものだったのに対し、“DBR1”は社内エンジニアであるテッド・カッティングの作品とされています。カッティングは、エンジンと「最悪」のギアボックスを除き、シャシー、足回りからボディ・デザインに至るまで、ほぼ全てを彼一人の手で作り上げたそうです。パワーユニットは戦後間もなくW.O.ベントレーが開発したDOHC6気筒ラゴンダ・エンジンをベースに年々改修が施されたものですが、“DBR1”では当初 2493cc.のものが用いられ(“DBR1/250”)、1957年からは2929cc.または2992cc.(“DBR1/300”)の排気量となりました。ルマン優勝時のスペックは、ウェバー50DCOキャブレターと9.3の圧縮比で、244bhp/6000rpm.とされていますが、同じく3リッタークラスであるフェラーリ・250テスタロッサの300bhp/7200rpmに比べると非力な感が否めません。 |
|
 |
|
| “DBR1”の一番の強味は、エンジンパワーよりも抜群の切れ味を誇ったハンドリングと言われており、当時も最も厳しいサーキットといわれたニュルブルクリンクで、並みいる強豪をなぎ倒し1957、58、59年の3年連続優勝を勝ち取った実績がこれを証明しています。59年のルマンを優勝に導いたロイ・サルヴァドーリは、「SUPER CG」誌とのインタビューで、「当時DBR1のシャシーにフェラーリのV12エンジンを積み、マセラーティのギアボックスを結びつけたなら、理想的なスポーツカーが生まれたでしょうね。でも…レースが退屈千万になったかもしれませんね」という言葉を残しています。 | |
 |
|
| 少し鈍重ですが安定性のあるエンジンと抜群のドライヴィングで一時代を謳歌した“DBR1”は合計5台が作られました。ルマンで優勝したこの車はシャシー・ナンバー2の“DBR1/2”で、これ以外にも1957年のニュルブルクリンク1000㎞、1958年ツーリスト・トロフィー優勝と最も輝かしい経歴を持ち現存しています。 “DBR1”は1957年から59年の3シーズンに16の国際レースに出場し、8レースで優勝を遂げましたが、特に1959年は最良の年となりました。ルマンをはじめ、シルヴァーストーン(S.モス)、ニュルブルクリンク(モス/フェアマン)、グッドウッドTT(モス/フェアマン/シェルビー)の四勝を挙げ、英国車初のワールド・スポーツカー・チャンピオンシップに輝いています。 |
|
| → 次のページへ | |
 Gallery へもどる Gallery へもどる Entrance Entrance |